道路を走る大型トラックを見ていると、タイヤの数や配置が車両によって異なることに気づいたことはありませんか?実は、大型トラックの「軸数」の違いは、単なるデザインの違いではありません。積載能力、走行性能、そして適した用途が大きく異なるのです。
運送業務において車両選びは非常に重要です。適切な軸数の車両を選ぶことで、業務効率の向上、コスト削減、そして安全性の確保につながります。
この記事では、大型トラックの三軸車、四軸車、前二軸車それぞれの特徴を解説します。走行性能、用途、強み、弱点、そして雪道での性能まで詳しくご紹介しますので、車両選びの参考にしてください。
1. 大型トラックの「軸」とは?基礎知識
軸の定義と役割
大型トラックにおける「軸」とは、車輪を支える車軸のことを指します。一般的に、左右のタイヤがセットになった部分を1軸と数えます。例えば、横から見た時に前に1つ、後ろに2つのタイヤがある場合、前1軸・後2軸の「三軸車」となります。
軸は単に車輪を支えるだけでなく、以下の重要な役割を担っています。
- 荷重の分散:積載した荷物の重量を複数の軸で分散させる
- 走行安定性の確保:路面との接地面積を増やし、安定した走行を実現
- 法規制への対応:道路への負担を軽減するための軸重規制をクリア
軸数によって何が変わるのか
軸数が増えることで、以下の点が変化します。
積載量の増加 軸数が多いほど、車両全体で支えられる重量が増加します。日本の道路運送車両法では、車両総重量の上限が定められていますが、軸数を増やすことでより多くの荷物を積載できるようになります。
安定性の向上 軸数が多いと路面との接地点が増えるため、重い荷物を積んだ状態でも安定した走行が可能になります。特にカーブや悪路での安定性が向上します。
法規制との関係 日本では、道路法によって1軸あたりの最大軸重が制限されています。一般的な道路では1軸あたり10トン(一定の条件下では緩和措置あり)という制限があるため、重量物を運ぶには軸数を増やす必要があります。
日本の道路法における軸重規制の概要
道路を傷めないよう、日本では以下のような規制が設けられています。
- 軸重制限:1軸あたり10トン以下
- 輪荷重制限:1輪あたり5トン以下
- 隣接軸重制限:隣り合う軸の合計で18トンまたは19トン以下(軸間距離により異なる)
これらの規制を守りながら最大限の積載を実現するために、運送業者は用途に応じて適切な軸数の車両を選択しています。
2. 三軸車の特徴と用途

2-1. 三軸車とは
三軸車は、前1軸・後2軸の構成が最も一般的な大型トラックです。前輪に2本、後輪に4本ずつ(合計8本)のタイヤで、左右合わせて計10本のタイヤを装備しています。十輪(じゅうりん)と呼ばれる事もあります。
後部の2軸は「ダブルタイヤ」と呼ばれる構造で、1つの軸に左右それぞれ2本ずつタイヤが装着されています。これにより、重量を効率的に分散させることができます。
大型トラックの中では最もスタンダードなタイプで、一般道でよく見かける大型トラックの多くがこの三軸車に該当します。
2-2. 走行性能
安定性と操縦性のバランス 三軸車は安定性と操縦性のバランスに優れています。後輪の2軸が荷重をしっかりと支えるため、積載時でも安定した走行が可能です。同時に、軸数が比較的少ないため、取り回しもしやすい特徴があります。
高速道路での直進安定性も良好で、長距離輸送でも運転疲労が少ないとされています。
燃費性能 四軸車と比較すると軸数が少ない分、転がり抵抗が小さく、燃費面で有利です。タイヤの本数が少ないため、メンテナンスコストも抑えられます。
一般的な三軸車の燃費は、走行条件にもよりますが、リッター3〜5km程度が目安となります。
小回り性能 ホイールベース(前輪と後輪の距離)が四軸車よりも短いため、比較的小回りが利きます。市街地での配送や、狭い道路での運転もしやすい設計です。
最小回転半径は車種にもよりますが、約12〜14メートル程度が一般的です。
2-3. 主な用途
一般貨物輸送 三軸車は汎用性が高く、さまざまな貨物輸送に使用されます。パレット積みの雑貨、家電製品、食品、日用品など、幅広い荷物に対応できます。
中距離・長距離輸送 燃費効率の良さと運転のしやすさから、中距離から長距離の定期輸送に適しています。高速道路を使った都市間輸送で多く活躍しています。
具体的な積載例
- ウイング車(箱型トラック)での雑貨輸送
- 平ボディでの建材・資材輸送
- 冷凍・冷蔵車での食品輸送
- 幌車での軽量かさ物輸送
最大積載量は車種や仕様により異なりますが、一般的に10〜13トン程度です。
2-4. 強み
汎用性の高さ 三軸車の最大の強みは、その汎用性です。さまざまな種類の荷物、さまざまな距離の輸送に対応できるため、運送会社にとって最も使い勝手の良い車両といえます。
コストパフォーマンス 車両価格は四軸車や前二軸車と比較して比較的安価です。また、タイヤの本数が少ないため、タイヤ交換などのメンテナンスコストも抑えられます。燃費も良好なため、運用コスト全体を抑えることができます。
運転のしやすさ 車体サイズと操縦性のバランスが良く、大型トラックの中では比較的運転しやすい部類に入ります。そのため、ドライバーの負担も少なく、長時間の運転でも疲れにくいという利点があります。
中古車市場の充実 三軸車は最も流通量が多いため、中古車市場も充実しています。予算に応じて選択肢が多く、導入しやすい点も魅力です。
2-5. 弱点
最大積載量の制限
四軸車と比べると積載能力に限界があります。非常に重い荷物や、容積は大きくないが重量のある荷物(鉄鋼製品、機械部品など)の輸送には不向きです。
法規制の範囲内で最大限積載しても、12〜13トン程度が限界となります。
重量物輸送には不向き
軸数が少ないため、1軸あたりの荷重が大きくなりがちです。そのため、軸重制限に引っかかりやすく、重量物を満載することが難しい場合があります。
特に、集中した重量物(建設機械、重機部品など)の輸送では、軸重配分に注意が必要です。
リアオーバーハング
右左折の際、車体後方が右折の際は左に、左折の際は右に大きくはみ出します。これは「ケツ振り」とも呼ばれ、右左折の際は気を付けなければなりません。
2-6. 雪道での走行性能
強み
- 適度な重量配分:後2軸に荷重が集中するため、ノーマル状態でも駆動輪のトラクション(グリップ力)が確保しやすい
- チェーン装着の容易さ:駆動する後輪の前部分の軸へのチェーン装着で十分な走破性を確保でき、作業効率が良い
- 小回りの良さ:軸間が短いため、雪道での切り返しや狭い除雪路での運転がしやすい
弱み
- 空荷時のスリップ:空車や軽積載の状態では後輪の荷重が不足し、坂道発進や凍結路面でスリップしやすくなる
また後輪の前側の軸のみ駆動するものが多いため、比較的滑りやすい - 横滑りのリスク:四軸車と比べて接地面積が少ないため、急なハンドル操作で横滑りしやすい
- 制動距離の延長:積載時は慣性が大きく、凍結路面では制動距離が大幅に延びるため注意が必要
降雪地域で三軸車を運用する際は、冬用タイヤの早めの装着と、チェーンの携行が必須です。
3. 四軸車の特徴と用途

3-1. 四軸車とは
四軸車は、前2軸・後2軸の構成が一般的な大型トラックです。前輪に4本、後輪に8本のタイヤを装備し、合計12本のタイヤで車両を支えます。
4軸の構造により、より多くの重量を分散して支えることができるため、重量物輸送や大量輸送に適しています。三軸車では運べない重量の荷物も、四軸車なら法規制内で運搬可能になります。
見た目にも圧倒的な存在感があり、タイヤの数の多さが特徴的です。
3-2. 走行性能
重量分散による安定性 四軸車の最大の特徴は、優れた重量分散能力です。荷重を広く分散させるため、重量物を積載した状態でも1軸あたりの荷重を軽減できます。
これにより、重い荷物を積んでいても安定した走行が可能で、カーブでの横転リスクも低減されます。高速走行時の直進安定性も非常に優れています。
路面への負担軽減 軸数が多いことで、同じ総重量でも路面への負担が分散されます。これは道路の保護にもつながり、特に重量物を運ぶ際の法規制クリアにも有利です。
走破性能 接地面積が広いため、悪路や軟弱地盤での走破性能も高くなります。建設現場への出入りなど、舗装されていない道路での作業にも対応しやすい特徴があります。
3-3. 主な用途
重量物輸送 最近ではこの四軸車が主流になりつつあります。鉄鋼製品、建設機械、大型設備、コンクリート製品、食品、飲料、日用雑貨など様々な輸送で活躍します。
建設資材運搬 砂利、砕石、セメント、鉄筋など、建設現場で使用される重量のある資材の運搬にも最適です。ウイング車だけでは無く平ボディ車でも四軸車を多く見かけるようになりました。
長距離大量輸送 容積が大きく重量もある荷物を、長距離輸送する際にも四軸車が選ばれます。最大積載量を活かした効率的な輸送が可能です。
具体的な積載例
- 平ボディでの鉄鋼製品輸送
- ウイング車での重量雑貨輸送
- 特殊車両での機械設備輸送
最大積載量は10〜13トン程度まで対応可能です。
3-4. 強み
高い積載能力 四軸車の最大の強みは、その圧倒的な積載能力です。三軸車では法規制上運べない重量の荷物も、四軸車なら合法的に輸送できます。
1台で多くの荷物を運べるため、往復回数を減らし、輸送効率を高めることができます。
軸重分散による法規制クリア 後部の3軸で荷重を分散できるため、1軸あたりの軸重を制限内に抑えやすくなります。重量物を運ぶ際も、軸重オーバーのリスクが低減されます。
重量物での安定走行 重い荷物を積んだ状態でも、優れた安定性を発揮します。急ブレーキや急カーブでも車両姿勢が安定しやすく、安全性の高い輸送が可能です。
長距離を重量物と共に走る場合でも、ドライバーの負担が少ないのも利点です。
3-5. 弱点
車両価格・維持費が高い 四軸車は車両本体価格が三軸車と比べて高額です。また、タイヤの本数が多いため、タイヤ交換などのメンテナンスコストも増加します。
12本のタイヤすべてを交換すると、費用は三軸車の1.2~1.4倍程度になります。ブレーキパッドなどの消耗品も軸数に応じて増えるため、維持費全体が高くなる傾向があります。
燃費効率 タイヤの本数が多い分、転がり抵抗が大きくなり、燃費は三軸車に劣ります。一般的に、リッター2.5〜4km程度が目安となり、三軸車と比べて10〜20%程度燃費が悪化します。
ただし、1台で多くの荷物を運べるため、トン・キロあたりの効率で考えれば必ずしも不利とは限りません。
小回りが利きにくい ホイールベースが長いため、三軸車と比較すると小回りが利きません。最小回転半径は15〜17メートル程度と大きく、狭い道路や市街地での運転には注意が必要です。
ただし三軸車と比べてリアオーバーハングがかなり小さいのでこれは大きなメリットと言えます。
3-6. 雪道での走行性能
強み
- 優れた重量分散:4軸で荷重が分散されるため、各タイヤへの負荷が均等になり、スリップしにくい
- 高いトラクション:タイヤの接地面積が広く、雪道での駆動力が安定している
- 安定した制動:ブレーキングポイントが多いため、重量物積載時でも比較的安定した制動が可能
- 横滑り耐性:接地面積が広いため、横風や路面の凹凸による横滑りに強い
- 駆動輪の多さ:後輪の2軸とも駆動するものがほとんどで、雪道でも優れた走行性能を発揮します。
弱み
- 回転半径の大きさ:三軸車に比べて回転半径が大きいため、切り返しや狭い所での運転が難しい
- 高い維持コスト:冬用タイヤが14本必要で、シーズンごとの交換費用が高額
- 見た目(人による):これは人によりますが、四軸車は三軸車に比べてタイヤが小さいので、特に古いドライバーはこの四軸車の見た目を嫌う人も多いです(笑)
僕自身も見た目は三軸車の方が好きですが、走行に関しては四軸車が一番運転しやすいと感じました。
4. 前二軸車の特徴と用途
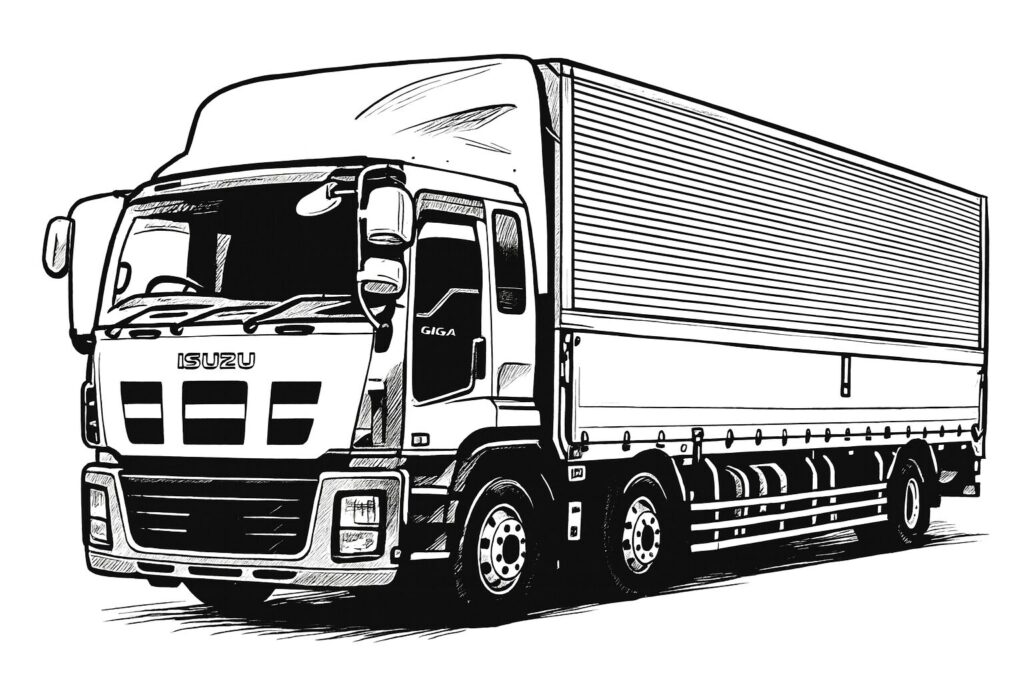
4-1. 前二軸車とは
前二軸車は、前2軸・後1軸の構成を持つ大型トラックです。前輪に4本、後輪に4本の合計8本のタイヤを装備します。
通常の大型トラックとは逆に、前方に多くの軸を配置することで、前方荷重に対応する設計となっています。この特殊な構造により、特定の用途において優れた性能を発揮します。
見た目の特徴として、運転席の後ろにもタイヤがあり、独特のフォルムをしています。
カンガルーのロゴの〇濃運輸のトラックはほとんどがこのフォルムですね。
4-2. 主な用途
センター間の雑貨輸送 拠点から拠点への雑貨の輸送で前二軸車が活躍します。主に高速道路移動で、センターに大量のトラックが集まり所狭しと横並びで積荷降ろし作業をする仕事ではこの前に軸車が活躍します。
タンクローリー 燃料、化学薬品、食品など、液体を運ぶタンクローリーにも前二軸車が使用されます。タンク自体の重量と液体の重量を合わせると前方荷重が非常に大きくなるため、前二軸構造が適しています。
4-3. 強み
直進安定性が高い ホイールベースが長くなるため、高速道路や長距離輸送時にまっすぐ走る安定感が増します。
バック(後退)がしやすい 後部のオーバーハングが短くなる構造のため、リヤタイヤが車体最後端に近く、正確な位置に寄せやすく狭い場所での後進操作も得意です。
ブレーキの安定性 前方に2軸(4輪)のタイヤで支えるため荷重が分散し、ブレーキ時の安定性が高く、車体の揺れが少なくなります。
経済性 10輪車(4軸車)と比べてタイヤ本数が少なく、タイヤの摩耗も分散するためタイヤ代やメンテナンスコストの節約につながります。
液体や揺れに弱い積載物に適する 前ニ軸車は縦揺れ(ピッチング)が少なく、タンクローリーのような揺れに弱い荷物に適しています。
4-4. 弱点
特殊用途に限定 前二軸車は、その構造上、用途が特定の車両に限定されます。一般的な貨物輸送には向いておらず、汎用性に欠けます。
そのため、運送会社が保有する車両としては、特定の業務専用となり、他の用途への転用が難しいという欠点があります。
車両価格が高い 特殊な構造のため、車両本体価格は通常の三軸車や四軸車と比較して高額です。また、受注生産や架装が複雑になるケースも多く、納期も長くなる傾向があります。
整備コストが高い 前2軸の操舵機構やサスペンションは複雑な構造となっており、整備には専門的な知識と技術が必要です。タイヤの本数も多いため、タイヤ交換などのメンテナンスコストも高くなります。
小回りが利かない 前二軸車では小回りが利かないため、狭い交差点などでは注意が必要です。
4-5. 雪道での走行性能
強み
- 優れた操舵性:前2軸操舵により、雪道でのハンドリングが安定し、滑りやすい路面でも進路修正がしやすい
- 制動の安定性:前方荷重が大きい状態での制動が安定しており、急ブレーキ時でも前輪がロックしにくい
弱み
- 空車時の後輪グリップ不足:空荷状態では後輪の荷重が不足し、後輪駆動車の場合は発進で苦労する
- 回転半径の大きさ:ホイールベースが長く、雪道での切り返しや狭い場所での運転が困難
- 液体の揺動リスク:タンクローリーの場合、凍結路面での急ブレーキや急ハンドルで液体が揺動し、車両が不安定になる危険性
前二軸車は特殊用途車両のため、雪道走行には特に慎重な運転が求められます。
まとめ
大型トラックの軸数は、単なる仕様の違いではなく、それぞれの用途に最適化された設計の結果です。この記事で解説した各軸車の特徴を改めて整理します。
三軸車は、最も汎用性が高く、一般的な貨物輸送に幅広く対応できるスタンダードなタイプです。コストパフォーマンスに優れ、運転のしやすさと十分な積載能力を兼ね備えています。中距離から長距離の定期輸送、一般雑貨の配送など、運送業の基本となる業務に最適です。
四軸車は、重量物輸送のスペシャリストです。三軸車では対応できない重量の荷物を、法規制を守りながら安全に運ぶことができます。建設資材や鉄鋼製品など、重い荷物を扱う業務には欠かせない存在です。車両価格や維持費は高くなりますが、積載効率の高さがそれを補います。
前二軸車は、特殊な用途に特化した車両です。センター間の雑貨輸送やタンクローリーなど、前方に重量が集中する構造の車両や狭いセンター内で大量の車両が横並びに所狭しと駐車する際に必須の設計で、前方荷重を安全に支えながら安定した走行を実現します。用途は限定されますが、その分野では代替が効かない重要な役割を果たしています。
雪道での性能については、積載時はどの軸車も比較的安定していますが、空荷時の運転には注意が必要です。降雪地域での運用では、冬用装備のコストとメンテナンスの手間も車両選定の重要な要素となります。
適切な軸数の車両を選ぶことは、業務効率の向上、コスト削減、そして何より安全性の確保につながります。運ぶ荷物の種類、走行距離、ルート、予算、そして気候条件など、さまざまな要素を総合的に考慮して、あなたの業務に最適な車両を選択してください。
ここまでお付き合い頂きありがとうございます。
この記事を読んでトラック運転手と言う仕事に少しでも興味を持って頂けたら幸いです。
このブログでは運送業界が全くの未経験の方でも安心して運送業界に挑戦していただけるよう、トラックドライバーに関する様々な記事を掲載しております。
良かったら他の記事もご覧ください。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
またお会いしましょう!



コメント